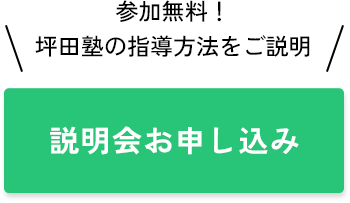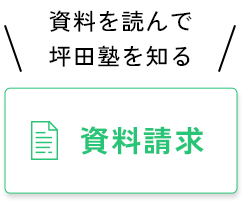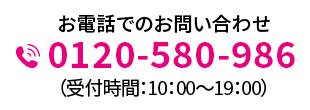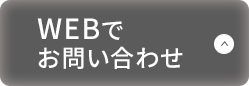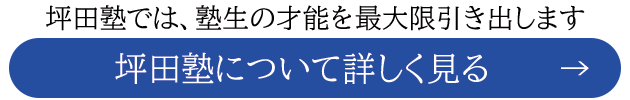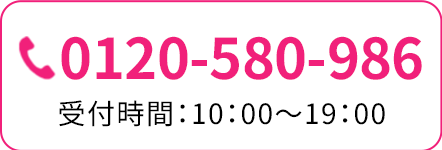夏休みは、大学受験に向けて学力を大きく成績を伸ばすことのできる貴重な期間です。しかし、「1日にどのくらい勉強すればいいの?」「何から手を付ければ良いのか分からない」と不安に感じている高校生のお子さんは多いのかもしれません。
大学受験対策として、限られた時間を有効に使うためには、高校生の夏休みの平均的な勉強時間を参考にしながら、具体的な学習計画を立て、より効率的に勉強に取り組む生活習慣を身につけることが大切です。
本記事では、高校生の理想的な夏休みの勉強時間や、受験生にとって夏休みがいかに重要か、そして効果的な勉強計画の立て方から学習内容と時間配分のコツまで、幅広く解説します。
目次(クリックで開閉)
・受験生の理想的な夏休み勉強時間は?学年別に紹介
┗高校1年生の夏休みの平均勉強時間
┗高校2年生の夏休みの平均勉強時間
┗高校3年生の夏休みの平均勉強時間
・受験生の夏休みの重要性
┗大学受験に向けた夏休みの位置づけ
┗夏休みは学力向上のチャンス
・受験生の夏休みの勉強計画の立て方
┗効果的な受験勉強スケジュールの作成方法
┗モチベーションアップ術
┗計画通りに進まない時の対処法
・【受験生の夏休み勉強時間】学習内容と時間配分のコツ
┗基礎固めとこれまでの復習が重要
┗どの科目に多くの時間を割くべきか
┗苦手科目の克服方法
┗バランス良く勉強するための時間配分のコツ
・受験生が夏休みの勉強時間を効率的に使うには
┗生活リズムを乱さないように注意
┗記憶に残りやすい勉強法
┗休憩時間設定がポイント
受験生の理想的な夏休み勉強時間は?学年別に紹介

大学受験に必要な勉強時間は、高校3年間を通して約3,000時間程度と言われています。これは中学生の3年間の高校受験に必要な勉強時間(約1,500時間程度)の倍以上です。さらに、最難関大(特に国公立大学)を志望校とする場合は、それ以上の勉強時間が必要になります。そんな中、まとまった休みを活用できる夏休みは、受験勉強を進める絶好のチャンスです。
まずは、高校1年生、2年生、3年生の夏休みの平均勉強時間を学年別に見ていきましょう。
高校1年生の夏休みの平均勉強時間
高校1年生の夏休みの平均勉強時間は、1日あたり3時間から4時間程度が目安です。
この時期は、まだ大学受験への意識が低いかもしれませんが、受験に必要な基礎力を確実に身につけるためには、ある程度の時間をかけて学習を始めることが重要です。また、高1のうちから決まった時間、机に向かう学習習慣をつけておくと、高2、高3でのより長時間の勉強にも対応しやすくなります。
4時間続けて勉強するのが難しい場合は、午前中を「勉強タイム」として固定するのがおすすめです。午前中に2時間程度集中して勉強し、午後や夜に1時間ずつなど、時間帯を分けて取り組めば、比較的楽に、無理なく学習を続けやすいことでしょう。
高校2年生の夏休みの平均勉強時間
高校2年生になると、受験を意識し始める人が増えるため、1日の平均勉強時間は4時間から6時間程度に増えるのが一般的です。
高3になってからの長時間勉強に慣れるためにも、高1の時より少しずつ勉強時間を増やしていくのがポイントです。勉強のスケジュールを「午前・午後・夜」のブロックに分け、それぞれ2時間ずつ勉強するイメージで机に向かってみましょう。
難関大学を目指す場合は、高校2年生のうちに1日8時間を目安に勉強時間を増やすことを検討すべきです。各ブロックの勉強時間を2時間から徐々に3時間へと延ばすなどの工夫が必要になります。
高校3年生の夏休みの平均勉強時間
高校3年生にとっては、本番までのカウントダウンが始まっているため、夏休みの時間の使い方が、合否に大きく影響します。そのため、夏休み中は1日8~10時間以上の勉強時間を確保するのが一般的です。
朝7時に起きて夜23時に寝る場合、食事や入浴などを除くと、自由に使える時間は約12時間程度。その中で8~10時間の勉強時間をしっかりと確保し、かつ集中して学習するためには、朝から夜までのタイムスケジュールを細かく立てて机に向かう必要があります。
午前中は脳がすっきりしていて集中しやすい時間帯です。早起きの生活を意識し、午前に3時間から4時間の勉強時間が確保できると、1日の学習にかなり余裕が生まれます。さらに、学習塾や予備校の夏期講習、大学ごとの対策講座を受講したり、移動中の隙間時間を活用したりするなど、勉強を上手に生活に組み込む工夫をすれば、1日10時間の勉強も可能になるでしょう。
受験生の夏休みの重要性
夏休みは学校の授業がなく、1日のほとんどを自分の予定で自由に使えます。そのため、受験生にとって夏休みは単なる長期休みではなく、長時間の勉強時間を確保し、学力アップのチャンスとして最大限活用できる、大学受験に向けた重要な時期と言えます。
大学受験に向けた夏休みの位置づけ
受験勉強に必要とされる約3,000時間を、高校3年生の期間(1年生の4月から3年生の1月頃まで)で単純に割ると、高校入学から入試まで毎日3時間程度の勉強が必要ということになります。しかし、学校行事や部活動、その他の予定がある日は、3時間の勉強時間を確保できないことも多いでしょう。
夏休みは40日間程度あります。1日8時間勉強すれば320時間、10時間勉強できれば400時間の学習時間を確保できます。このように、普段の勉強時間の不足分を補うという意味でも、受験生の夏休みは非常に重要なのです。
学校の授業が一時的にストップするこの休み期間は、自分の苦手な分野の把握や克服にじっくり取り組んだり、志望校の過去問に挑戦したりと、自分のペースで戦略的・計画的に学習を進められる貴重な時間です。夏休みの努力が、2学期以降の学力アップや志望校合格の可能性を大きく左右すると言っても過言ではありません。
夏休みは学力向上のチャンス
夏休みは普段よりも時間に余裕があるため、学力を一気に引き上げる大きなチャンスです。例えば、高校3年生が1日8~10時間の学習時間を確保できれば、苦手分野の克服や基礎の復習、応用問題への取り組みまで、具体的な学習が可能になります。また、長時間を活用して問題集などで演習量をこなせば、知識を「得点力」に結びつけるための対策も十分にできます。
学年に関わらず、夏休みは周りのライバルに差をつける時期でもあります。ただし、目に見える明確な成果を出すためには努力の積み重ねが必要であり、やる気の維持が非常に重要です。夏休みに学力が一気に伸びる人は、毎日決まった時間に勉強を始める学習習慣が身についており、午前・午後・夜の学習時間を確実に決めて、生活と勉強のリズムができていることがほとんどです。目標から逆算して計画を立て、自分のモチベーションを維持しながら、時間だけでなく内容の伴った効率的な学習に集中することが、夏休みの大幅な学力アップにつながるのです。
受験生の夏休みの勉強計画の立て方
秋以降の学力アップや、周りとの差のつける上で大きな意味を持つ夏休み。合格という成果を出すためには、効率的な学習を進めるための勉強計画を作成し、着実に実行していく必要があります。ここからは、効果的な勉強スケジュールの作成方法や、勉強を継続していくためのコツを紹介します。
効果的な受験勉強スケジュールの作成方法
夏休みの勉強で成果を上げるためには、目標から逆算したスケジュール作成がポイントとなります。まずは、夏休み終了時に達成していたい目標を明確にしましょう。
<夏休み終了時の達成目標例>
・英単語を300語暗記する
・各教科の基礎問題集を1周完了する
・苦手な部分を集中的に復習する
・毎日演習問題に取り組み、計算ミスを減らす
このような学習内容の目標と一緒に、「早起きして午前中に3時間勉強する」「スマホの使用時間を1日1時間以内にする」など、時間の活用に関する目標を設定するのがおすすめです。
また、1日単位の具体的なやることリストも作成しましょう。例えば、「英語長文読解1題+数学の基礎問題10問」のように、1日に終わらせたい内容を明確にしておくことで、迷わずスムーズに勉強を開始できます。計画を立てる際は、大まかな時間配分と具体的な学習内容を紙などに明記しておくと良いでしょう。午前は暗記科目、午後は演習問題など、時間帯ごとに科目や内容を分ける工夫をすると、集中力の維持に効果的です。
さらに詳しい勉強計画の立て方については、「勉強計画の立て方を知って効率アップ!挫折しないための6つのポイントも紹介」を参考にしてください。
モチベーションアップ術
夏休みは学習時間を確保しやすい一方で、子どもにとってはモチベーションの維持が難しくなりがちな時期でもあります。そんな時は、以下のような方法を活用して、気持ちと思考をうまくコントロールしていきましょう。
<モチベーション維持のコツ例>
・1週間ごとに小さな報酬を設定する
・息抜きをしてリフレッシュする
・完全な休みの日(休息日)を決めておく
・勉強環境を変えてみる(自宅、図書館、予備校など)
・オープンキャンパスに参加してみる
※「オープンキャンパスの服装は制服?私服?身だしなみマナーと気を付けるべきポイント」を参考にしてください。
1日の目標を達成したらチェックを入れる、ご褒美を設定するなど、努力を可視化し、達成感を経験していくことは、やる気を維持する上で大事なポイントです。
また、適度な息抜きでリフレッシュすることも大切です。「この日は完全にオフ」と休息日を設定すれば、気分転換になり、翌日のやる気向上にもつながります。普段と違うカフェや図書館、塾の夏期講習や自習室で勉強するなど、環境を変えるだけでも新鮮な気持ちになれるでしょう。
さらに、「なぜこの大学に行きたいか」という志望校への気持ちを定期的に確認することもおすすめです。オープンキャンパスに参加したり、志望校のパンフレット資料や大学の写真を机に貼ったりするなど、大学生活をイメージできる工夫を実践することで、集中して勉強に打ち込みやすくなります。
なお、坪田塾では、生徒一人ひとりの性格を9つのタイプに分け、その性格タイプに合った指導を通じて、勉強のモチベーション維持を支えています。
計画通りに進まない時の対処法
長い夏休みの期間中、綿密に計画を立てていても、予定通りに進まない日があるのは当然のことです。
そんな時に重要なのは、その理由を分析し、柔軟に計画を修正することです。例えば、時間が不足していたのか、集中力が続かなかったのか、やる気が低下していたのかなど、計画していた内容を網羅できなかった理由を特定し、振り返ってみましょう。時間不足なら1日の学習内容や勉強方法の見直しが必要ですし、集中力が続かないケースではスケジュールの調整が必要かもしれません。また、やる気が不足していたケースなら、モチベーションアップのための工夫を取り入れるなど、翌日以降に軌道修正できる対策を見つけて実践する必要があります。
予定通りにいかなかったとしても、それが問題というわけではなく、失敗でもありません。体調が優れない日や、急な予定変更が入る場合もあるでしょう。そのため、完璧を求めすぎず、「8割程度達成できれば十分」といった気持ちで取り組むのがポイントです。数日程度の予備日を設けて、余裕のある無理のないスケジュールを作成しておきましょう。
【受験生の夏休み勉強時間】学習内容と時間配分のコツ
夏休みの勉強計画を立てる際は、学習内容とともに時間配分を意識したスケジュール作成が重要です。貴重な時間を最大限活用するためには、学習の効率をアップさせる学習内容の選択と時間の配分を意識しましょう。
基礎固めとこれまでの復習が重要
夏休みは、これまでの学習内容を復習する絶好のタイミングです。基礎をおろそかにすると、将来的に応用問題や難解な内容を学習する際に、想像以上に時間が必要になってしまいます。「基礎固め」と「復習」に重点を置きながら、学力の基礎を強化しておきましょう。
まずは、英単語や文法、数学の公式や基礎問題、社会の年号や重要事項、理科の基本原理や法則などを、繰り返し反復してインプットすることが重要です。特に、苦手な問題や過去に解けなかった問題に再挑戦することで、理解を深め、自信につなげることもできるでしょう。
単に学習済みの内容を確認するだけでなく、問題演習を通じて理解を定着させることがポイントです。「わかる」と「できる」の違いを意識し、「解けたつもり」で放置していた単元や、模試でミスをした部分などを徹底的に復習することが、秋以降の成績アップにつながるでしょう。
どの科目に多くの時間を割くべきか
受験勉強では、科目ごとに「優先順位」をつけることも重要です。志望校の受験科目や出題傾向を意識し、特に重点を置くべき科目に長時間を配分しましょう。
例えば、英語は多くの大学で配点が大きいため長時間を割くのが一般的です。後に続く単元を理解するために前の単元の理解が不可欠な、積み上げ型の科目でもあるため、基礎をおろそかにせず、時間をかけて学習しておく必要があります。
また、比較的暗記が多い理科や社会は、効率的に勉強を進めることが可能かどうかが重要なポイントとなります。隙間時間などを効果的に活用できるかどうかが鍵となるでしょう。
そして、「得意科目を伸ばすこと」と「苦手科目の克服」の両立が重要です。得意科目は、入試で安定した点数を獲得するために、学力を維持可能な程度の時間を確保しておく必要があります。ただし、苦手科目を後回しにしすぎると、入試本番までに必要な学力に到達できない可能性があります。得意科目の学習を維持しつつも、より優先的に苦手科目に時間を割いて苦手を克服するなど、自分の得意不得意に応じた学習計画を意識して計画を作成しましょう。
大学受験のための英語の勉強法については、「大学受験のための英語勉強法の正解・不正解とは?合格を目指す学習のポイント」を参考にしてください。
苦手科目の克服方法
苦手克服のための方法として、「なぜこの科目や分野が苦手なのか」を分析し、効果的な対策を実行する必要があります。苦手という意識は、理解不足、知識不足、演習不足が理由で発生しているのが一般的です。基礎があやふやなのか、解法の理解が不足しているのかによっても、対策は変わってきます。まずは、自分が何が原因でつまずいているのかを特定し、苦手克服のための具体的な対策を検討しましょう。
苦手だと思う単元は、やみくもな反復ではなく、理解を深めることが大切です。例えば数学なら、「この公式はどのように導きだされるのか」といった過程を理解するなど、単なる解法の暗記ではなく、原理を理解できるよう意識しましょう。
また、短い時間でも毎日継続することが苦手克服のポイントです。午前中の30分だけでも集中して苦手科目に取り組む学習習慣を確立し、復習の頻度を上げていくことで、知識が定着しやすくなり、苦手意識を払拭しやすくなります。
苦手科目の学習時には、なかなか理解が進まず、もどかしい思いをするかもしれません。しかし、小さな成功体験を積み重ねることで自信がつき、やる気につながり、ますます学習が進むという好循環が生まれます。例えば、苦手だった問題が解けるようになったり、理解できる単元が増えたりする度に、紙に書き出してみる、できるようになった量に応じてご褒美を準備するなどの工夫を試すと、苦手科目の勉強も続けて取り組みやすくなるでしょう。
バランス良く勉強するための時間配分のコツ
効率的に学力をアップさせるためには、科目の偏りを回避し、バランス良く勉強することも大切です。1日単位でバランスを取るのが難しい場合は、週単位や、午前は主要科目・午後は暗記科目など、時間帯や日で配分したりするのが有効です。
また、人の集中力には波があるため、自分が最も集中できる時間を意識した勉強法もおすすめです。一般的に午前中は集中力が高い時間帯です。この時間に得意科目を学習してペースを作ったり、逆にやる気の出にくい難易度の高い科目や苦手科目に取り組んでしまったり、自分なりのやり方を探って工夫をしてみましょう。夜に復習系の軽めの学習を配置するなど、コンディションやリズムに合わせた時間配分を意識することで、学習の効果をさらに高めやすくなります。
受験生が夏休みの勉強時間を効率的に使うには
受験生が夏休みの勉強時間をより効率的に活用するためには、勉強時間や時間配分、学習内容から計画を立てることはもちろん、さらに学習効率をアップさせるコツを実践することが大切です。
生活リズムを乱さないように注意
夏休みは学校がないので自由な時間が増え、夜型の生活になりがちです。朝寝坊をして昼間に眠気に襲われるといった、不規則な生活に陥ることも少なくありません。しかし、大学受験の入試は午前中に実施されるのが一般的です。試験当日に備えて早起きの生活を習慣化しないと、テスト本番中に集中力が切れてしまう可能性もあります。
毎日、朝8時~9時台には学習をスタートすることを目標に、早起きを心がけましょう。また、同じ時間に起床・就寝して生活リズムを安定させることで、集中力や暗記力が高まります。規則正しい生活を維持することは体調不良の予防にもなり、毎日の学習効率アップに貢献します。
記憶に残りやすい勉強法
人の記憶はインプットしただけでは定着しないため、演習(アウトプット)を積極的に取り入れるのがおすすめです。例えば、英単語を暗記した直後にテスト形式で書き出してみたり、読んだ参考書の内容を自分の言葉で要約したり、頭に入れた知識を再現してみたりと工夫をしてみましょう。
また、エビングハウスの忘却曲線によれば、人の記憶は1日後、3日後、1週間後など、一定期間をおいて繰り返し復習を行うと定着が進むと言われています。復習のタイミングを意識しながら学習計画を作成するのもおすすめです。
さらに、睡眠中は記憶が整理されやすく、知識をより長く覚えていられるようになると言われています。学習内容が記憶に定着しやすくなるよう、就寝前に暗記科目の復習を行うなどの工夫も取り入れてみましょう。
休憩時間設定がポイント
長時間机に向かっていても、集中せずにダラダラと勉強を続けていては、効率が悪いどころか、かえって疲労やストレスを溜めてしまいます。そこで大切なのが、メリハリをつけた休憩の方法を意識することです。
人間の脳機能は、ウルトラディアンリズム(生体リズム)と呼ばれる90分周期で集中と休息を繰り返していると言われています。そのため、90分間集中して勉強した後に15分の休憩でリフレッシュすることで、次の90分も高い集中力を維持できるサイクルを作りやすくなります。共通テストや二次試験の試験時間は60~80分程度であるため、試験本番に集中力を保つ訓練にもなるでしょう。
あるいは、ポモドーロテクニックを活用し、25分学習したら5分休憩するのもおすすめです。短期間集中すれば良いと思えることで心理的なハードルが下がるため、特にモチベーションが低い時や苦手科目に取り組むときに、行動の第一歩を踏み出しやすくなります。また、集中力が切れる前に休憩を取れることから、脳疲労を抑制し、パフォーマンスの維持にも貢献します。さらに、短時間で達成感を感じられ、やる気の維持にもつながるでしょう。
ただし、深い思考が必要な学習は、短時間で中断が入るポモドーロテクニックが向かないケースもあります。数学の応用問題や英作文など、高い集中力で取り組むことが必要な内容は、90分しっかり集中するスタイルを取るなど、バランス良く休憩を挟むことを心がけましょう。
自宅での勉強の効率を上げる方法については「勉強の効率を上げる自宅学習法6選」も合わせて参考にしてください。
-
-
映画『ビリギャル』でおなじみの個別指導塾!坪田塾とは
坪田塾は中学校1年生~高校3年生、高卒生(浪人生)を対象にした個別学習塾・予備校です。首都圏(東京・埼玉・千葉)、名古屋、大阪、兵庫に22校舎、日本全国に指導を提供するオンライン校を加えて全23校舎を展開しています。
-
坪田塾では、学力や学校のスケジュールに合わせて勉強できる個別プログラムに加え、9つの性格タイプに合わせた教育心理学に基づく指導によって、子ども一人ひとりを支えて寄り添う、「子」別指導に力を入れています。
この科学的に証明された学習法により、多くの受験生の偏差値を短期間で大きく上げて、難関校合格へと導いています。料金も1時間1,530円~と、通いやすい料金体系です。
「ビリギャル」のモデルにもなった塾に興味がある方は、ぜひ無料体験授業を受講してみてください。