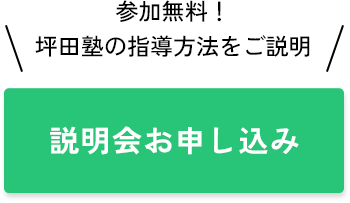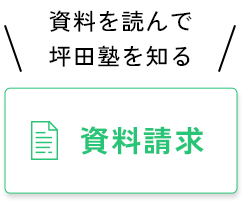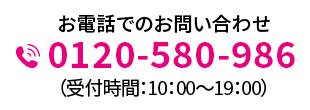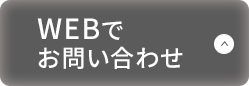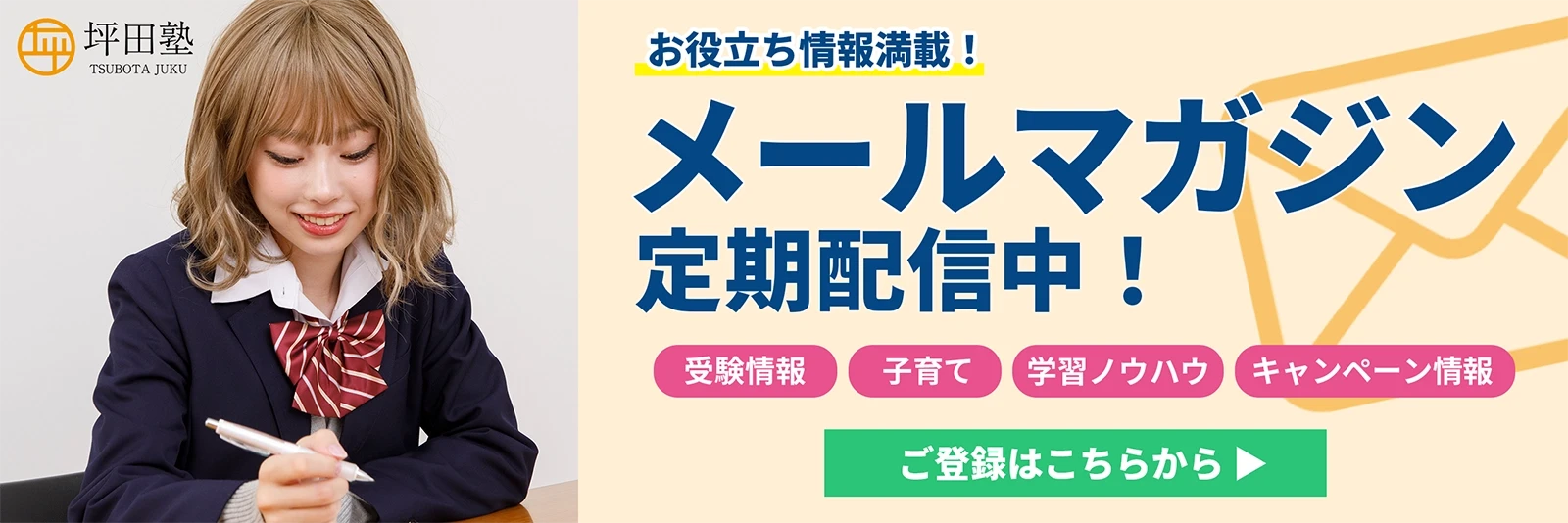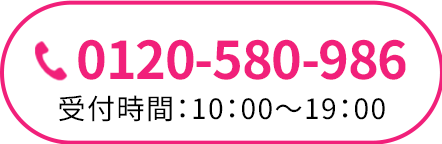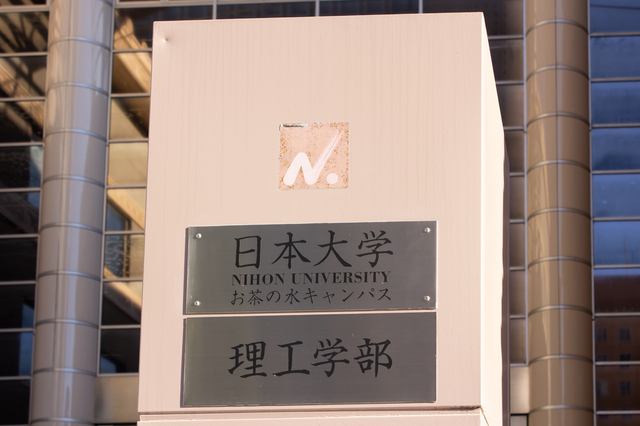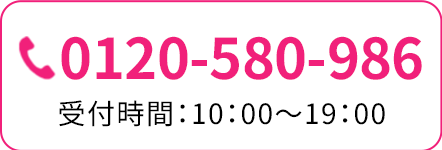旧帝大とは?各大学特徴は?偏差値をランキング形式で解説
大学入試を意識し始め、「旧帝大を目指したい」「早慶上智やMARCHと同レベルの国公立大に合格したい」と、日々勉強に励んでいる受験生は多いのではないでしょうか。
旧帝大(旧帝国大学)は、早慶上智・早慶上理・MARCH、GMARCH、SMART、日東駒専・関関同立などと同様、大学の偏差値や知名度などの入試難易度によってグループ分けされた呼称の一つです。数ある日本の大学の中でも、トップレベルの国公立大学群として位置づけられているのが、この旧帝大です。全国各地の高い学力を持った学生がこぞって志望する大学群です。
本記事では、旧帝大とはどんな大学なのか、各大学の特徴を詳しくご紹介します。また、最新データに基づく偏差値ランキング、受験を勝ち抜くための戦略と対策、そして高校生が志望校を選ぶ上で役立つ入試情報まで、詳しく解説していきます。
目次(クリックで開閉)
・旧帝大(きゅうていだい)とは
・旧帝大7校の特徴
┗東京大学の特徴~研究者やリーダーを創出!最も歴史ある大学
┗京都大学の特徴~自由な校風が特徴の関西トップ大学~
┗大阪大学の特徴~学生の数は国立大学の中で最多~
┗名古屋大学の特徴~立地面でも東西から人気の大学~
┗東北大学の特徴~日本で3番目の帝国大学として創立~
┗九州大学の特徴~2~3割の学生が留学生!国際色豊かな大学~
┗北海道大学の特徴~獣医学部と水産学部は旧帝大で唯一~
・旧帝大の偏差値ランキング
・旧帝大受験のための戦略と対策
┗旧帝大入試の特徴
┗旧帝大合格に必要な学力レベル
┗旧帝大の受験勉強のポイント
旧帝大(きゅうていだい)とは
「旧帝大(きゅうていだい)」とは、旧帝国大学を略した呼び名です。戦前の日本において、「帝国大学」という名前で設立された国立大学のことを指します。
「帝国大学」は、1886年に公布された帝国大学令によって創立された、日本の旧制高等教育機関です。1947年の日本国憲法の施行に伴い教育制度が大きく変化し、「帝国大学」という名称が廃止され、その翌年に「国立大学」として再編、新しく生まれ変わりました。
その後、規模や研究レベル、入試難易度など、様々な面でトップクラスを維持している7つの大学を「旧帝大」や「七帝大(ななていだい)」と呼び、他の国立大学と区別するようになりました。それが以下の7大学です。
・東京大学(東大)
・京都大学(京大)
・大阪大学(阪大)
・名古屋大学(名大)
・東北大学(東北大)
・九州大学(九大)
・北海道大学(北大)
旧帝大の偏差値は学部によって異なりますが、最難関の東大・京大は約65~73、難関大とされる阪大・名大・東北大・九大・北大も約60~70とされています。
私立大学と比較すると、MARCHや関関同立よりも難易度は高く、早慶上智の中でも上位に位置する早慶と同等か、それ以上のレベルと言えます。
学費が私立大学の半分程度であること、研究環境が充実していること、そして就職に強いといった面から、多くの学生が旧帝大を目指しています。
旧帝大7校の特徴

ここからは、旧帝大7校それぞれの特徴と魅力を、さらに深く掘り下げてご紹介します。
東京大学の特徴~研究者やリーダーを創出!最も歴史ある大学~
東京大学は、首都圏に3つの主要キャンパスを構えています。
・本郷キャンパス(法・経済・文・農・工・医・薬・理・教育学部)→東京都文京区
・駒場キャンパス(教養学部)→東京都目黒区
・柏キャンパス(一部の研究科・先端研究施設)→千葉県柏市
東大の大きな特徴は、1・2年次は全員が教養学部に所属し、駒場キャンパスにて幅広い分野の教養を学んだ後、3年次に進級する際に、専門的に学びたい学部・学科を選択し、本郷キャンパスでの学習に移行するという流れにあります。
柏キャンパスは、新領域創成科学研究科など一部の大学院生が学ぶキャンパスとなっており、この他、医科学研究所(白金キャンパス)など、数多くの研究施設を保有しています。
東京大学は、開成学校と東京医学校を前身として、1877年に設立されました。1886年に「帝国大学」、1897年に「東京帝国大学」に改称し、現在では10学部を擁する総合大学へと発展しました。
日本最古の帝国大学として、最も権威がある大学です。「世界最高水準の知の創造」を理念に掲げ、幅広い学問分野の基礎をしっかり固め、社会の最前線で活躍できるリーダーの育成に力を入れています。文系・理系を問わずあらゆる分野で高いレベルを誇りますが、特に法学・経済学・理学・医学の分野では突出しており、自由な学問の発展と文理を超えた総合的な学びを推奨しています。
国からの研究費配分額も多く、充実した環境による学術研究を通じて国内外の課題解決に貢献できる人材の育成に努めており、卒業生の多くは、日本の官僚・公務員、研究者として日本の発展を支えています。また、三菱グループ、トヨタ、ソニー、GoogleやAmazonなど国内外の大手民間企業への就職にも非常に強い大学です。
京都大学の特徴~自由な校風が特徴の関西トップ大学~
京都大学は、京都府内に3つの主要キャンパスを有しています。
・吉田キャンパス(総合人間・農・法・経済・教育・理・医・薬学・文学部)→京都府京都市左京区
・宇治キャンパス(自然科学・エネルギー系の研究所)→京都府宇治市
・桂キャンパス(工学部・大学院工学研究科)→京都府京都市西京区
この他、複合原子力科学研究所や、宇宙物理研究を行っている飛騨天文台、海洋生物研究の拠点となる白浜水族館などの施設も有する大学です。
1897年に「京都帝国大学」として、東京大学に次ぐ2番目の帝国大学として設立されました。現在では10学部を擁する総合大学へと発展を遂げています。京都大学の最大の特徴は、何と言っても「自由な学風」です。東大とは異なり、学生・教員がともに主体的に考え、既存の枠にとらわれない学びを追及するとともに、権威や常識にとらわれずに自分の考えを持つ姿勢を重視しています。独創的な研究が盛んに行われており、理学・工学・医学・能楽などの自然科学分野に強く、ノーベル賞受賞者も多数輩出している大学です。
卒業生の多くは、大学教授や研究者として活躍しており、その数は東大に次いで全国2位を誇ります。また、任天堂、京セラ、村田製作所など、関西を拠点とする大手民間企業とのつながりも強く、就職先として多くの学生が選択しています。さらに、自由な校風の影響で、スタートアップ企業やベンチャー企業の創業者が多い大学でもあります。
大阪大学の特徴~学生の数は国立大学の中で最多~
大阪大学は、大阪府内に3つのキャンパスを構えています。
・吹田キャンパス(工・人間科学・医・薬・歯学部)→大阪府吹田市
・豊中キャンパス(文・経済・理学・基礎工学・法学部)→大阪府豊中市
・箕面キャンパス(外国語学部)→大阪府箕面市
この他、社会人向け講座や研究拠点である中之島センター、理論物理学研究を行う南部洋一記念研究室、医学研究や診療拠点である附属病院など、多様な施設を有しています。
吹田キャンパスにある美しいイチョウ並木は、校章にもデザインされるなど阪大のシンボルのひとつです。多くの学生や地域の人々が訪れる名所にもなっており、大学の伝統と精神を象徴する存在となっています。
大阪大学は、1931年に前身の大阪医科大学を母体として創設されました。当初から医学・工学を重視していましたが、現在では理学・人文社会系にも強く、幅広い分野をカバーする11学部を擁する総合大学へと発展しています。
大阪大学が掲げるのは、「実学」の理念。社会の発展に貢献できる人材の育成に力を入れており、パナソニックやダイキンなど関西経済・産業界を支える企業との連携も非常に盛んです。共同研究などを通して、技術革新を支援・後押ししています。
また、外国語学部を持つ唯一の旧帝大として、多言語教育に強みを持ち、国際社会で活躍する人材育成にも注力しています。
自由でオープンな校風も大阪大学の特徴・魅力の一つ。京大ほど自由すぎず、東大ほど固苦しくない、絶妙なバランスの「阪大らしさ」を大切にしており、教師との距離が比較的近く、授業中のやりとりがカジュアルでアットホームなことでも知られています。
医学・工学系は特に高い割合で大学院に進学している他、パナソニックやダイキンなどの製造大手メーカー、Amazonなどの外資系企業、コンサルティングファームなどへの就職にも強い大学です。
名古屋大学の特徴~立地面でも東西から人気の大学~
名古屋大学は、愛知県内に3つの主要キャンパスを構えています。
・東山キャンパス(法・経済・文・教育・理・工・情報・農学部)→愛知県名古屋市千種区
・鶴舞キャンパス(医学部)→愛知県名古屋市昭和区
・大幸キャンパス(医学部保健学科)→愛知県名古屋市東区
1939年、旧帝大の中では最も新しい「名古屋帝国大学」として設立されました。
名古屋大学が掲げるのは「挑戦的な研究と実学の融合」という基本理念。「不屈の精神(Nagoya Spirit)」を合言葉に、既存の枠にとらわれず、未知の分野に果敢に挑戦する精神を持つ人材の育成に力を入れています。また、学問の理論的な探求に加えて、産業界との連携を重視し、社会に貢献できる実践的な力を養うことにも力を入れています。
理学・工学・医学に強く、特に物理・化学分野でノーベル賞受賞者を複数輩出しています。また、トヨタ自動車やデンソーなど、地域を代表する企業との結びつきも強く、産学連携が活発に行われています。
京大ほど自由奔放ではなく、堅実で謙虚な学風を「名大らしさ」と表し、「学力や研究力は非常に高いけれど、それをことさらに誇示しない」、そんな独自の文化が根付いているのも特徴のひとつです。
物理学や材料工学の分野では、大学院に進学する学生や、研究機関で活躍する卒業生が多くいます。就職先としては公務員や地方自治体職員、さらに、トヨタやデンソーなどの自動車産業への就職にも強いのが特徴です。
東北大学の特徴~日本で3番目の帝国大学として創立~
東北大学は、宮城県内に4つの主要キャンパスを有しています。
・片平キャンパス(本部・法学研究科などの研究施設)→宮城県仙台市青葉区
・川内キャンパス(文・教育・法・経済学部)→宮城県仙台市青葉区
・青葉山キャンパス(理・工・農・薬学部)→宮城県仙台市青葉区
・星陵仙台市青葉区
この他、地震研究拠点である地震・噴火予知研究観測地点に加え、世界トップクラスの金属研究施設である金属材料研究所を有する大学です。
1907年、日本で3番目の帝国大学「東北帝国大学」として創立されました。現在では10学部を擁する総合大学へと発展を遂げています。
日本で初めて「大学院重点化」を導入し、「研究第一」を理念に掲げ、何よりも研究を最優先にする大学です。実学尊重を重んじ、理論だけでなく社会に役立つ実践的な学問を重視しています。また、「門戸開放」の理念のもと、1913年に日本で初めて女子学生の入学を許可した大学でもあります。
材料科学、工学、医学などの分野で特に高い評価を得ており、金属・ナノテクノロジー・航空宇宙などの分野では世界をリードする研究成果をあげています。東日本大震災以降は、社会貢献にも力を入れており、震災復興や防災研究の中心にもなっています。企業との共同研究など、産学連携が活発な大学でもあります。
理系学部で大学院への進学率が高くなっており、防災・復興関連の公的機関や研究機関で活躍する卒業生も多くいます。三菱重工や日立製作所、IHIなど、大手メーカーのエンジニア職への就職にも強みを持っている大学です。
九州大学の特徴~2~3割の学生が留学生!国際色豊かな大学~
九州大学は、福岡県内に3つの主要キャンパスを有しています。
・伊都キャンパス(法・経済・文・教育・理・工・農・共創学部)→福岡県福岡市西区
・病院キャンパス(医・歯・薬学部)→福岡県福岡市東区
・大橋キャンパス(芸術工学部)→福岡県福岡市南区
この他、地熱エネルギー研究を行う別府キャンパス、先端物理研究を行う筑紫キャンパスを有する大学です。
1911年に「九州帝国大学」として設立され、現在では九州地方で最大規模の12学部を擁する総合大学へと発展しています。
アジアとの学術交流を重視しており、「開かれた大学」を理念に掲げています。そのため、海外留学生が学生の2~3割を占めており、国際色豊かな大学です。
多様性を尊重し、国際的視野を持った人材育成とともに、エネルギーや環境問題などの社会問題への取り組みにも力を入れている大学です。さらに、「進取の精神」を大切にし、新しい分野に積極的に挑戦する姿勢を育くむことにも力を入れています。
環境科学やバイオテクノロジー分野で高い評価を得ており、大学院に進学する学生や、研究職として活躍する卒業生が多くいます。また、公務員や地方自治体職員、九州電力やENEOSなどのエネルギー・化学関連業界への就職にも強い大学です。
北海道大学の特徴~獣医学部と水産学部は旧帝大で唯一~
北海道大学は、北海道に2つのキャンパスを持つ大学です。
・札幌キャンパス(法・経済・文・教育・理・工・医・歯・薬・獣医・農学部)→北海道札幌市北区
・函館キャンパス(水産学部)→北海道函館市
この他、動物科学研究を行う静内研究牧場や、森林・生体学研究を行う北方生物園フィールド科学センター、環境学・森林学研究を行う苫小牧研究林などを有する大学です。
1876年に「札幌農学校」として開校され、1918年に「北海道帝国大学」に改称されました。広大なキャンパスと自然豊かな環境で勉学に励むことができ、現在では12学部を有する総合大学へと発展しました。
「札幌農学校」の創設に携わり、初代教頭を務めたウィリアム・スミス・クラーク博士の「Boys, be ambitious!」は、あまりにも有名です。「金銭や名声ではなく、高い志を持ち、より大きな目的のために努力せよ」という意味が込められており、この言葉が北海道大学の掲げる「フロンティア精神」の原点となっています。
北海道大学はさまざまな分野に挑戦し、社会貢献を重視するとともに、北海道という広大なフィールドを活かし、農業・水産業・酪農などの分野で、地域産業と連携した実学や研究を推進。世界的な視野を持つ人材の育成に力を入れています。
農学・水産学・寒冷地研究の分野で国内トップクラスの実績を誇り、特に環境科学や気象研究で世界的な評価を得ています。卒業生の多くは、環境省、JAXA、気象庁などの研究機関や公的機関で活躍しています。さらに、ホクレンやニッスイ、マルハニチロなど農業・水産関連企業への就職にも強いのが特徴です。
旧帝大の偏差値ランキング

各予備校が発表しているデータによると、旧帝大の偏差値は学部によって大きく異なります。
<大学偏差値の目安>
東京大学:約67~73
京都大学:約65~70
大阪大学:約60~65
東北大学:約60~65
名古屋大学:約57~63
九州大学:約 55~65
北海道大学:約55~63
最も偏差値が高いのは、全ての学部で67以上を誇る東京大学。中でも、理科三類は73と、突出した難易度です。
京都大学も、医学部の70超えをはじめ、ほとんどの学部で65以上の高い偏差値をマークしています。ただし、工学部や農学部の一部、医学部人間健康科学科では、偏差値60~63程度の学部も見受けられます。
大阪大学は、医学部の偏差値が70と高いものの、他の学部は60~65程度。外国語学部や医学部保健学科では、60を切る場合もあります。
他の大学においても、学部によって大きなばらつきがあります。
このように、学部によって偏差値に幅はあるものの、大学全体の難易度で比較すると、東京大学と京都大学が最もレベルが高く、次いで大阪大学と東北大学、その下に名古屋大学・九州大学・北海道大学が続く、という大学ランキングになると考えられるでしょう。
旧帝大受験のための戦略と対策
旧帝大は偏差値が高い最難関大学群。合格を勝ち取るためには、共通テストと2次試験という、2つの厳しい試験を乗り越えなければなりません。大学ごとに異なる2次試験の出題傾向を把握し、対策を練ることはもちろん、共通テストで高得点を獲得することも重要で、莫大な勉強時間が必要です。難易度が高いうえ、勉強すべき範囲が非常に幅広いことから、合格に必要な学力レベルに到達するためには、しっかりとした学習計画を立て、十分な勉強時間を確保するなどの受験対策が不可欠となります。
旧帝大入試の特徴
旧帝大に合格するためには、共通テスト(7教科)と、各大学が独自に実施する2次試験の2つをクリアしなければなりません。
私立大学であれば、共通テスト利用入試であっても3教科程度で受験できることが一般的ですが、大多数の国公立大学では、共通テストで6教科を受験する必要があります。理系学部志望であっても、国語や社会を受験する必要がありますし、文系学部志望であっても数学の知識が必須になります。2025年度からは、新教科「情報」も加わり、より幅広い学習が求められるようになります。
さらに、旧帝大の2次試験の入試問題は、難易度の高さ、出題範囲の広さ、記述式の問いが多いことなどから、非常に難しいことで知られています。知識だけで解ける問題はほとんどなく、解答に至るまでのプロセスや論理的思考力が問われるのが特徴です。
<難解だとされる2次試験問題の例>
・数学:数列の性質を考察しながら解く記述式の問題
・英語:難解なテーマにおける自由英作文
・物理:計算だけでなく物理現象を理論的に説明する記述問題出題
・現代文:高度な哲学・言語学・社会学がテーマの、抽象度の高い評論文の要約問題や考察の記述問題
・古文・漢文:登場人物の心情を読み取る問題や本文の要旨をまとめる問題
・世界史・日本史:論述量が多く、単なる知識の羅列ではなく「比較」や「因果関係」の明確な説明を求められたり、歴史の流れを理解したうえで具体的な事例を挙げた説明を求められたりする
記述量は200~600字が当たり前で、文章を論理的に組み立てる力や構成力が求められます。「なぜそうなったのか?」という理由を説明させる問題も多く、単語や文法、公式、年号や用語、教科書の内容を丸暗記しているだけでは、太刀打ちできません。さらに、東大や京大では、答案の「美しさ」も評価の対象になると言われており、乱雑な解答は減点対象となる可能性もあります。
各大学の出題傾向を分析・予測し、頻出分野を重点的に学習するためには、過去問対策や模試、専門塾、予備校などのカリキュラムを効果的に活用し、勉強法に取り入れていくことが重要です。
旧帝大でも、一部の学部で学校推薦型選抜や総合型選抜が導入されていますが、一般的な国公立大学に比べると、その数は少ないのが現状です。医学系・国際系・理工系など、実施している学部が限られている上、高い学力、特別な実績、課題提出、面接、小論文が求められます。東大の場合、高校時代の研究・表彰歴・課外活動が重視されたり、共通テストの受験が必須であったりすることも。出願条件の詳細をしっかりと確認し、十分な対策を講じる必要があります。
旧帝大合格に必要な学力レベル
旧帝大合格のためには、共通テストと2次試験の両方で高得点を獲得することが求められます。そのため、非常に高い学力が必要となることは言うまでもありません。
<旧帝大の共通テスト得点率目安>
・東京大学:87~93%
・京都大学:81~91%
・大阪大学:74~90%
・名古屋大学:79~94%
・東北大学:75~94%
・九州大学:69~90%
・北海道大学:74~88%
学部によって差はありますが、東大・京大は共通テストで9割近く、それ以外の大学でも最低75%、上位層では85~90%の得点が必要になります。共通テストは、基礎的な学力を測る試験であるため、苦手科目を作らずに、安定した高得点を取ることが求められます。
さらに、2次試験では、記述式の難問に対応できる、高度な思考力と論述力が求められます。共通テストレベルを超える難問も出題されるため、単語、文法、公式など、教科書レベルの基礎知識は完璧にマスターしておくことが必須となります。その上で、身につけた知識を応用し、自分の言葉で論理的に記述できる力を養うことが、旧帝大合格の最低条件と言えるでしょう。
旧帝大の受験勉強のポイント
旧帝大に合格するためには、高校1年生など、早い段階から大学受験を意識し、コツコツと勉強を進めることが大切です。苦手科目を放置せず、都度一つ一つ克服しておくこと、基礎を確実に固めておくことが、共通テストで高得点を取るための土台となります。
さらに、安定して高得点を取れる力と、時間内に正確に問題を解く力を鍛える必要があります。まずは、教科書レベルの知識を完璧にし、基礎を固めましょう。その後、スピードと正確性を意識しながら、問題演習を繰り返し行うことが重要です。ケアレスミスを防ぐ対策も徹底的に行いましょう。過去問や模試を活用し、共通テスト特有の問題形式に慣れておくことも大切です。
2次試験対策としては、共通テスト対策で培った基礎力と、本質を理解する力に加え、記述力を徹底的に鍛える必要があります。過去問演習を繰り返し行ったり、専門塾で添削指導を受けたりしながら、答案の質を向上させましょう。
旧帝大の合格可能性を高めるためには、高校3年間で、およそ3,000~5,000時間の学習時間が必要だとされています。高1・高2の間は平日2~3時間、休日4~6時間、高3では平日は6~8時間、休日は10~12時間の学習を確保することが理想的です。
ただし、やみくもに長時間机に向かえばいいというわけではありません。勉強の質を上げる工夫も必要です。例えば、移動時間などのスキマ時間を活用し、英単語やリスニングの学習に充てる、朝型の生活習慣で集中力を高める、アウトプットを意識し問題演習では自分の言葉で回答を説明できるようにする、など、学習時間と効率を両立させることが、旧帝大合格を勝ち取る近道となることでしょう。本記事に掲載されている情報を参考に、ぜひ自分に合った勉強法を見つけてください。
映画『ビリギャル』でおなじみの個別指導塾!坪田塾とは
坪田塾は中学校1年生~高校3年生、高卒生(浪人生)を対象にした個別学習塾・予備校です。首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)、名古屋、大阪、兵庫に24校舎、日本全国に指導を提供するオンライン校を加えて全25校舎を展開しています。
坪田塾では、学力や学校のスケジュールに合わせて勉強できる個別プログラムに加え、教育心理学に基づく9つの性格タイプに合わせた指導・声掛けによって、子ども一人ひとりを支えて寄り添う、「子」別指導に力を入れています。
この科学的に証明された学習法により、多くの受験生の偏差値を短期間で大きく上げて、難関校合格へと導いています。料金も1時間1,640円~と、通いやすい料金体系です。
「ビリギャル」でおなじみの坪田塾に興味がある方は、ぜひ無料体験授業を受講してみてください。
◆坪田塾の校舎一覧はこちら

無料
学習相談実施中!
学力診断をもとに専用の学習計画をご提案します