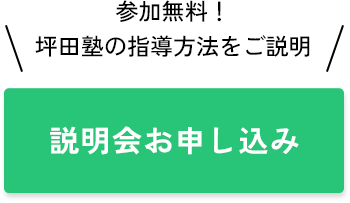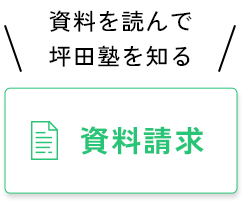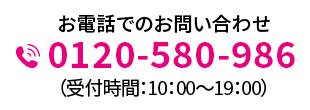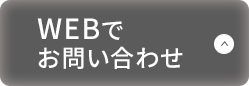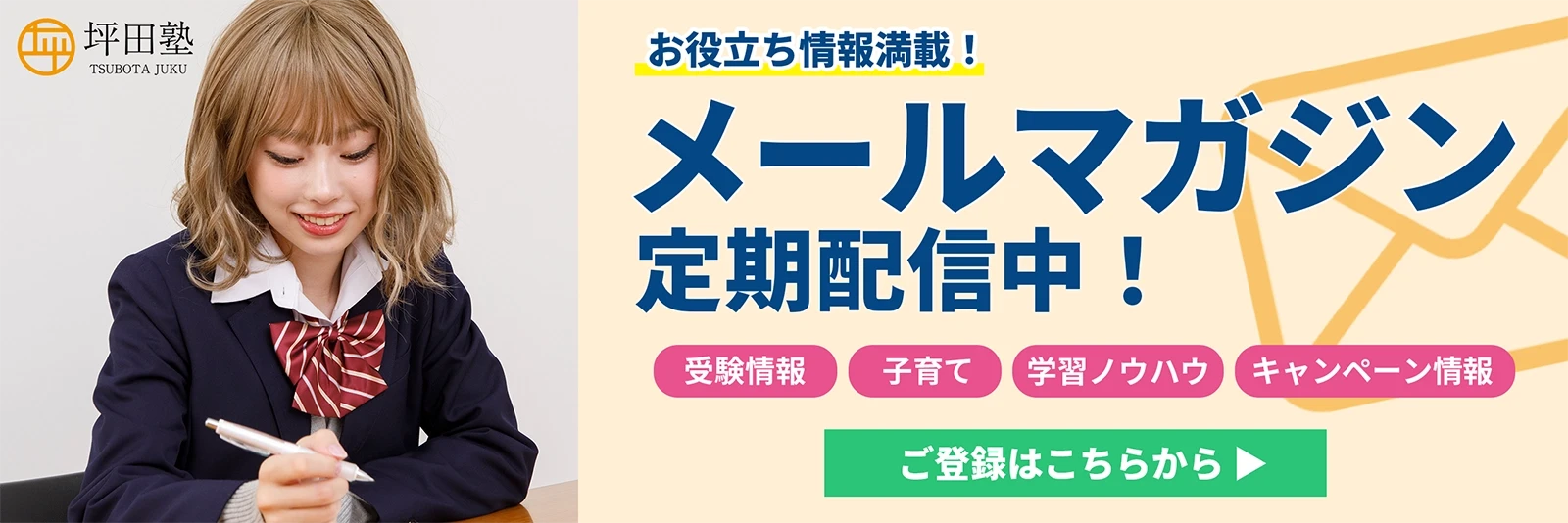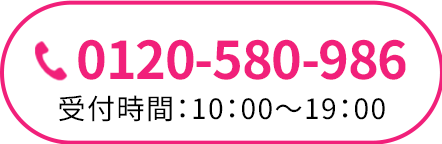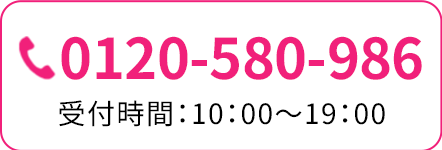模試の判定結果は、受験生にとって今後の学習計画を考えるための重要な指標です。
しかし、その結果をどう受け止め、次にどう活かせばよいのか、迷う人も少なくありません。
本記事では、A判定からE判定までの合格基準や、それぞれの判定が出た際の考え方を丁寧に解説します。
さらに、学年別の判定結果のとらえ方や、勉強の進め方、結果が思わしくなかった場合の具体的な学習戦略も分かりやすくまとめました。
判定結果を正しく受け止め、志望校合格に向けた次の一歩を踏み出すために、ぜひ最後までご覧ください。
目次(クリックで開閉)
・模試の合格判定のランクと考え方
┗A判定・B判定
┗C判定
┗D判定・E判定
・学年別でみる模試のとらえ方
┗高校1年生
┗高校2年生
┗高校3年生
┗高卒生(浪人生)
・模試の判定結果が悪い場合は志望校を変えたほうがよいのか
・模試の合格判定を左右する要因
・模試の判定結果が出た時の注意点
・模試の判定結果を活かすためのポイント
┗ポイント①つまずいている箇所を確かめる
┗ポイント②受験科目を見直す
┗ポイント③他の受験者のレベルを押さえる
・模試の判定結果が出た後の勉強で意識したいこと
┗何度も復習する
┗志望校の出題傾向をつかむ
┗インプットとアウトプットの割合を調整する
・模試の判定に関するよくある質問
┗模試の判定は信頼できる?
┗E判定でも志望校の大学に合格できる?
模試の合格判定のランクと考え方
模試の合格判定は、一般的にA判定からE判定までの5段階で評価されます。
現在の自分がどの判定に該当するかによって、今後の学習方針を調整していく必要があります。
それぞれの判定が持つ意味と、そのとらえ方を詳しく見ていきましょう。
A判定・B判定
一般的に、A判定は合格可能性80%以上、B判定は65%程度とされ、その時点では合格圏にいると判断されます。
ただし、A判定でも5人に1人は不合格となる可能性があり、B判定では約3人に1人が不合格になる計算です。
合格の可能性が高いとはいえ、決して油断はできません。この判定は、これまでの学習方法が間違っていなかったことの証明と位置づけ、気を緩めずに学習を継続することが大切です。
特に浪人生の場合、現役生の追い上げを考慮すると、A判定、最低でもB判定を安定して維持する意識で取り組みましょう。
C判定
C判定は、合格可能性が約50%であることを示す判定です。
まさに合否のボーダーライン上であり、ここからの取り組み次第で合格にも不合格にも転じる可能性があります。
注意したいのは、模試を受けた時期によって、C判定の意味合いが変わる点です。
例えば、部活を引退したばかりの高校3年生が夏の模試でC判定を取った場合は、秋以降の本格的な受験勉強で成績を伸ばせる余地が大いにあります。
しかし、入試本番が近い秋以降の模試でC判定だった場合は、同じC判定でもB判定寄りかD判定寄りかを見極めた上で、場合によっては志望校の再検討も必要になってきます。
D判定・E判定
D判定の合格可能性は35%程度、E判定では20%以下とされており、数字だけ見ると厳しい状況といえます。
ただし、模試の判定はあくまでも「現時点での」学力を示したものに過ぎません。
特にE判定は多くの受験生が1度は経験するものであり、決して珍しいものではないということを覚えておきましょう。
本気で逆転合格を狙うのであれば、まずは現状の課題を冷静に分析することが何よりも大切です。
どの科目・どの分野で点数を落としているのか、ケアレスミスなのか、理解不足なのかなどを洗い出し、重点的に対策すべき単元を明確にしましょう。
どうしても挑戦したい大学であれば、判定にとらわれず努力し続ける価値は十分にあります。 しかし、E判定から合格を目指すことが大きな負担になる場合は、併願校を含めた進路全体をもう一度見直すことも、前向きな選択の一つといえるでしょう。
学年別でみる模試のとらえ方
 模試は、受ける学年によってその判定の重みや活かし方が異なります。 それぞれの段階で何を意識すべきか、学年別に詳しく見ていきましょう。
模試は、受ける学年によってその判定の重みや活かし方が異なります。 それぞれの段階で何を意識すべきか、学年別に詳しく見ていきましょう。
高校1年生
高校1年生のうちは、模試の判定結果に一喜一憂する必要はまったくありません。 合格可能性を測るというよりも、自分の得意・苦手な分野を発見し、学習の方向性を定めるための「健康診断」のようなものです。
模試の目的はあくまでも、自分の現在地を客観的に知ることにあります。
例えば、「数学で文章題になると点が取れない」「英語の長文読解に時間がかかりすぎる」といったように、普段の授業では気づきにくい弱点を明確にしてくれます。 もし苦手分野に気が付いたなら、場合によっては中学校の内容にまでさかのぼって学び直す勇気も必要です。
この時期に基礎を丁寧に積み重ねておくことが、高校3年生になってからの成績の伸びに大きくつながります。
高校2年生
高校2年生の模試でも、判定に過敏になる必要はありません。しかし、結果を今後の学習にどう活かすかを具体的に考えることが大切です。
結果から自分の現在地を把握するだけでなく、「どの科目にどのくらい力を入れるべきか」という、受験に向けた戦略を立てるための材料として活用しましょう。
例えば、理系志望で数学の応用問題で失点が多いなら、その分野を優先的に強化するといった具体的な対策が必要です。
また、高校2年生の秋以降は、記述模試や全国模試など、より本番を想定した形式のテストも増えてきます。
模試の形式に慣れ、時間配分を意識して解く練習を始めておくと、高校3年生からの本格的な受験対策へスムーズに移行できるでしょう。
高校3年生
高校3年生にとって、模試の判定は進路に直結する重大な指標です。
特に秋以降の模試の結果は、出願校を最終決定する際の大きな判断材料となるため、判定を真剣に受け止める必要があります。
ただし、判定結果だけですべてを決めるのでなく、志望校へのこだわりや将来のビジョンも加味して、総合的に選択することが大切です。 A判定だからと油断せず、D・E判定だからと諦めるのではなく、教科や科目ごとの結果を冷静に分析し、残された時間で何ができるかを考え、戦略的に学習と出願計画を進めていきましょう。
高卒生(浪人生)
高卒生(浪人生)は、模試の判定を現役生よりもシビアに受け止める必要があります。
高校生よりも1年多く勉強しているというアドバンテージがある以上、A判定、少なくともB判定を安定して取れる状態を目指すべきといえます。
現役生は夏に部活動を終え、受験勉強に本格的に集中し始めるため、秋以降に急激に成績を伸ばすケースが少なくありません。
高卒生(浪人生)が同じペースで勉強を続けていると、成績や順位が相対的に下がってしまう可能性があります。
A判定が出ていても決して慢心せず、常に本番の試験を見据えて、高いレベルでの学習を継続しましょう。
模試の判定結果が悪い場合は志望校を変えたほうがよいのか
模試でD判定やE判定が出たからといって、すぐに志望校の変更を考える必要はありません。
判定結果はあくまでも「模試時点での」学力を示すものであり、今後の努力次第で十分に挽回できる可能性があるからです。
夏の時点までに基礎がある程度身に付いているのであれば、秋以降の演習を通して、本番までに学力を大きく伸ばすことも可能です。
大切なのは、判定結果から目を背けず、自分の課題を冷静に洗い出し、具体的な改善に取り組むことです。その上で、どうしても成績が伸び悩む場合に、あらためて進路を見直すかどうかを判断しましょう。
模試の合格判定を左右する要因
模試の判定結果は、自分の実力だけでなく、模試の種類・難易度・受験者層によっても左右されます。 主要な模試の違いを、以下の表にまとめました。
| 模試の種類 | 受検者層 | 特徴 |
|---|---|---|
| 進研模試 | 大学受験をしない生徒を含む | 判定が甘めに出る傾向があり、母集団のレベル幅は広め |
| 河合塾模試(全統) | 大学受験を前提とした生徒 | もっとも多くの受験生が利用。出願戦略の参考にしやすい |
| 駿台模試 | 難関大志望の生徒が中心 | 難易度が高く、判定も厳しめに出やすい |
このように、どの模試を受けるか、どの集団の中で比較されるかによって、同じ実力でも偏差値や合格判定が大きく変動します。
模試の特性を理解したうえで、客観的に、判定結果を受け止めるようにしましょう。
模試の判定結果が出た時の注意点

判定結果は、あくまでも現時点での学力を示す一つの目安であり、志望校への合否を決定するものではありません。
たとえA判定であっても、油断は禁物です。
それは、今までの学習の方向性が間違っていないことの証にはなりますが、安心して勉強の手を緩めてしまうと、他の受験生にあっという間に追い抜かれてしまいます。
また、C判定からE判定が出てしまった場合でも、必要以上に落ち込む必要はありません。
受験本番まで半年以上残されている段階であれば、基礎の再定着や学習計画の見直しによって、挽回できる余地は大いにあります。
模試はゴールではなく、現在の自分の現在地を正確に把握し、ゴールまでの道のりを修正するためのツールです。
判定結果を過信しすぎず、過小評価もしすぎないようにしましょう。
模試の判定結果を活かすためのポイント
模試はただ受けて結果を見て終わりではなく、その結果を分析し次のアクションにつなげることで、初めて価値が生まれます。
具体的には、以下の3つのポイントを押さえることが大切です。
- ・つまずいている箇所を確かめる
- ・受験科目を見直す
- ・他の受験者のレベルを押さえる
それでは、詳しく見ていきましょう。
ポイント①つまずいている箇所を確かめる
模試を受けたら、まず自分がどの分野で、なぜつまずいたのかを明確にすることが大切です。
模試の成績表には「分野別成績」や「小問別の正誤一覧」が詳しく掲載されていることが多く、得意・不得意が数値として可視化されます。
例えば、英語で文法問題は正解できているのに長文読解で大きく失点しているようなら、語彙力や読解力に課題がある、とみなすことができます。
こうした分析を通じて自分の弱点が理解できれば、重点的に取り組むべきポイントが明確になり、勉強法の見直しにもつながります。
模試の結果を最大限に活かし、学習の軌道修正を行いましょう。
ポイント②受験科目を見直す
もし、どうしても得点が伸び悩む科目がある場合は、受験科目そのものを考え直すことも一つの方法です。
特に私立大学を目指す場合は、2~3科目の選択制入試を活用して、自分の得意な科目に絞って受験することもできます。
基礎からの学び直しが必要な教科を勉強し続けるよりも、得意分野で確実に高得点を狙うほうが、効率的で合格可能性は高まります。
科目の変更を決めたら、迅速に計画を軌道修正し、受験本番までの残り時間を有効に使いましょう。
ポイント③他の受験者のレベルを押さえる
模試を受ける大きな目的の一つは、同じ志望校を目指すライバルたちの中で、自分がどの位置にいるのかを客観的に把握することです。
成績表には、志望校における順位や合格者平均点との差などが示されています。
合格者平均点に対して、自分があと何点足りていないのかが分かれば、「どの科目をどれほど強化すれば合格ラインに届くのか」を見極めやすくなります。
他の受験生との相対的な位置関係を把握し、合格までに必要な努力量を明確にした上で、今後の学習計画に役立てましょう。
模試の判定結果が出た後の勉強で意識したいこと
模試を受けた後は、以下のことに取り組むことが大切です。
- ・何度も復習する
- ・志望校の出題傾向をつかむ
- ・インプットとアウトプットの割合を調整する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
何度も復習する
模試は解くだけで満足してしまう人が多いものの、その後の「復習」こそが重要です。
解けなかった問題はもちろん、たとえ正解していても自信がなかった問題は必ずチェックしましょう。
「なぜこの選択肢が正解なのか」「なぜ間違えたのか」を自問自答しながら、自分の言葉で説明できるようになるまで思考を深掘りすることが復習の質を高めるコツです。
間違えた問題の解説を読んでも理解できない場合は、そのままにせず、必ず学校や塾の先生に質問して解決しましょう。
志望校の出題傾向をつかむ
模試の結果と同時に、志望校の出題傾向とのギャップを意識することが大切です。
全国模試は、全国の受験生に向けた標準的な問題で構成されており、大学ごとの出題傾向までは反映されていません。
志望校独自の出題傾向を把握するには、過去問を数年分解くことが有効です。
過去問を分析することで、「英語は長文が必ず2題出る」「数学では図形問題が頻出する」など、その大学ならではの特徴を理解できます。
模試の判定は参考情報ととらえ、最終的には志望校の過去問に合わせた対策を徹底しましょう。
インプットとアウトプットの割合を調整する
効率よく学力を伸ばすには、知識を覚える「インプット」と問題を解く「アウトプット」のバランスを意識することが大切です。
知識をただ覚えるだけでは応用が効きにくく、かといって演習ばかりでは理解があいまいになることもあります。
模試でミスが多かった分野は、まず教科書や参考書で基礎知識を再確認(インプット)し、その後、問題演習(アウトプット)で知識を定着させる、という流れが効果的です。
模試の判定に関するよくある質問
最後に、模試の判定に関して多くの受験生が抱く疑問についてお答えします。
- ・模試の判定は信頼できる?
- ・E判定でも志望校の大学に合格できる?
それぞれ解説します。
模試の判定は信頼できる?
ある程度は信頼できますが、絶対的なものではありません。
A判定だからといって必ず合格できるわけではなく、反対にE判定だからといって合格の可能性がゼロというわけでもありません。
あくまでも、「その模試を受けた時点での合格可能性」を示す目安ととらえましょう。
また、先述の通り、模試の種類によって判定の出やすさには大きな違いがあります。
進研模試は、学校単位で受験する生徒も多く、母集団のレベルが幅広いため、比較的高めの判定が出やすい傾向があります。一方、駿台模試は難易度が高く、受験者層もハイレベルなため、同じ実力でも判定が厳しく出がちです。
例えば、進研模試でA判定だった人が駿台模試ではC判定になる、といったケースも珍しくありません。
より精度の高い判定を知りたい場合は、志望校別模試や、共通テスト型模試の受験がおすすめです。
E判定でも志望校の大学に合格できる?
模試の結果がE判定であっても、志望校に合格する可能性はあります。
E判定は「その模試を受けた時点での合格可能性が20%以下」であることを示すものですが、裏を返せば「5人に1人は合格する可能性がある」という意味でもあります。
また、E判定は決して珍しいものではなく、模試によっては受験者の半数以上がE判定になることもあります。
出題範囲や受験者層のレベルによって判定は大きく変動するため、一度の結果に必要以上に落ち込む必要はありません。
大切なのは、結果を事実として冷静に受け止め、合格に向けた次の一歩を踏み出すことです。
【まとめ】模試の判定を正しくとらえ、大学受験対策を進めよう
模試はゴールではなく、自分の現在地を確認し、志望校までの道のりを修正するためのツールです。
結果が出たら必ず復習を行い、過去問研究を通じて学習をブラッシュアップし、インプットとアウトプットのバランスを意識しながら着実に実力を伸ばしていきましょう。 判定結果に一喜一憂するのではなく、そこから何を学び、次にどう行動するかが、合格を左右します。
なお、坪田塾では模試結果と生徒一人ひとりの個性を分析し、オーダーメイドの学習計画を作成します。「反転学習」を通して自ら考え学ぶ自走力を養い、大学受験はもちろん、その先の社会で活躍するための「一生モノの学習力」を育みます。
映画『ビリギャル』でおなじみの個別指導塾!坪田塾とは
坪田塾は中学校1年生~高校3年生、高卒生(浪人生)を対象にした個別学習塾・予備校です。首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)、名古屋、大阪、兵庫に24校舎、日本全国に指導を提供するオンライン校を加えて全25校舎を展開しています。
坪田塾では、学力や学校のスケジュールに合わせて勉強できる個別プログラムに加え、教育心理学に基づく9つの性格タイプに合わせた指導・声掛けによって、子ども一人ひとりを支えて寄り添う、「子」別指導に力を入れています。
この科学的に証明された学習法により、多くの受験生の偏差値を短期間で大きく上げて、難関校合格へと導いています。料金も1時間1,640円~と、通いやすい料金体系です。
「ビリギャル」でおなじみの坪田塾に興味がある方は、ぜひ無料体験授業を受講してみてください。
◆坪田塾の校舎一覧はこちら

無料
学習相談実施中!
学力診断をもとに専用の学習計画をご提案します